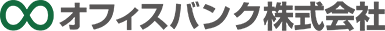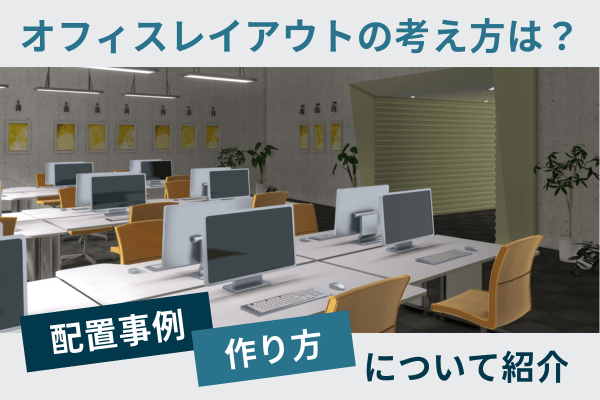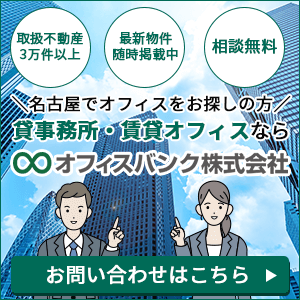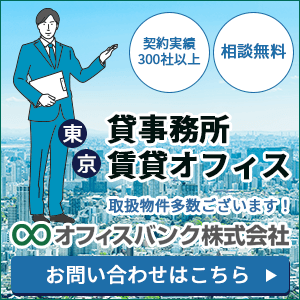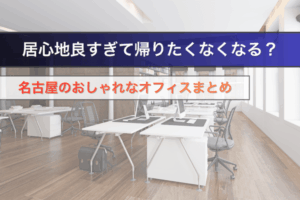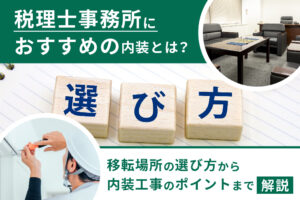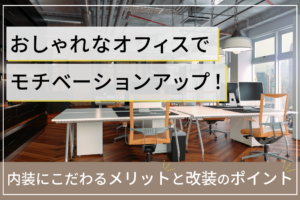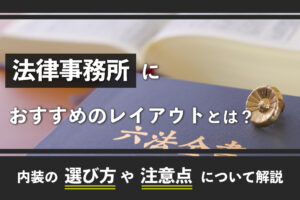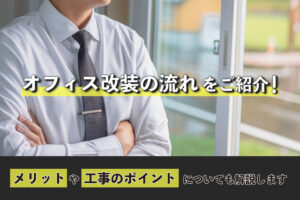「オフィスレイアウトはどうやって考える?」
「オフィスレイアウトの作り方は?」
オフィスレイアウトの考案は、見切り発車でスタートすると時間がかかったり、失敗したりするリスクがあります。
そのため、事例をもとに基本となる形を決めて、社員の理想に合ったデザインに仕上げることが大切です。
- 対向型レイアウト
- 並列型レイアウト
- 背面型レイアウト
- ブース型レイアウト
- クロス型レイアウト
- ブーメラン型レイアウト
当記事では、オフィスレイアウト考案のポイントや、機能的なオフィスレイアウトの事例をご紹介します。
レイアウト設計に悩んでいる方は、是非参考にしてみてください。
オフィスレイアウトのデスク配置6パターン
オフィスレイアウトのデスク配置事例を、以下の6パターン紹介します。
- 対向型レイアウト
- 並列型レイアウト
- 背面型レイアウト
- ブース型レイアウト
- クロス型レイアウト
- ブーメラン型レイアウト
業務スタイルに合わせて、適切なレイアウトを選択することが大切です。
それぞれ基本的なレイアウトについて、以下で詳しく見ていきましょう。
対向型レイアウト

対向型レイアウトは、デスクを向かい合わせに配置する形式で、オフィスで最も一般的な配置方法の一つです。
このレイアウトは、社員同士が顔を合わせやすく、コミュニケーションが取りやすい点が特徴です。
特に、チームや部署ごとの連携が重要な業務に適しています。
また、スペース効率が良く、限られたオフィスの面積を最大限活用できるメリットもあります。
さらに、対向型にすることで、個々の作業領域を確保しつつも、隣や向かいの社員と情報共有がしやすくなるため、バランスが取れた配置といえるでしょう。
並列型レイアウト

並列型レイアウトは、デスクを横一列に並べる配置形式で、シンプルかつ効率的なレイアウトの一つです。
この配置は、社員同士が同じ方向を向いて作業するため、集中力を維持しやすい点が特徴です。
また、限られたスペースを有効活用できるため、狭いオフィスでも取り入れやすい形式です。
特に、業務上の連携が必要ない個々の作業が多い場合や、一定の作業工程を繰り返す業務に適しています。
背面型レイアウト

背面型レイアウトは、デスクを背中合わせに配置する形式で、個々の作業に集中しやすい配置方法です。
社員同士が向かい合わないため、視線が気にならず、プライバシーを保ちながら作業を進めることができます。
このレイアウトは、チームでの会話よりも、個別の業務が多い職場や、集中力を重視したい環境に適しています。
一方で、社員間のコミュニケーションが減る可能性があるため、共用スペースや打ち合わせの場を別途設ける工夫が必要です。
ブース型レイアウト

ブース型レイアウトは、個々のデスクを仕切りで囲み、社員一人ひとりのプライバシーや集中力を重視した配置方法です。
特に、個別作業が多い職場や情報の取り扱いが厳密に求められる業務に適しています。
また、仕切りを利用して各ブースに収納スペースや掲示板を設けることで、機能的な作業空間を作り出すことができます。
一方で、社員同士のコミュニケーションが減る可能性があるため、休憩スペースや会議室で交流を促進する工夫が必要です。
クロス型レイアウト

クロス型レイアウトは、テーブルを縦横に交差させて配置するスタイルで、オフィス内の動線を工夫した設計が特徴です。
この配置では、デスクが交差する形で配置されるため、ジグザグの通路が生まれ、社員の動線が固定化しにくくなります。
その結果、異なる社員同士が自然に接する機会が増え、コミュニケーションの活性化が期待できるでしょう。
また、クロス型レイアウトはスペースの有効活用にも優れており、広さに限りがあるオフィスでも柔軟に導入可能です。
ブーメラン型レイアウト

ブーメラン型レイアウトは、デスクを湾曲した形状で配置する形式で、デザイン性と機能性を兼ね備えたレイアウトの一つです。
この配置は、デスクの形状や配置がブーメランのようなカーブを描くため、自然な動線が生まれ、社員が快適に移動しやすくなるのが特徴です。
また、湾曲したデスクは、作業スペースを広く確保しながらも、隣り合う社員との距離感を適度に保つことができるため、集中しやすい環境作りができます。
さらに、デザイン性の高さから、オフィス全体の印象を洗練されたものにする効果も期待できます。
オフィスレイアウトの座席運用4パターン
オフィスレイアウトの座席運用は、以下の4パターンが基本となっています。
- 固定席
- ABW
- フリーアドレス
- グループアドレス
配置以外にも、座席のスタイルを決めることはレイアウトにおいてとても重要です。
以下で詳しく解説します。
固定席
固定席は、社員ごとに決まった座席を割り当てる座席運用のスタイルです。
この運用では、各社員が自分専用のデスクや収納スペースを持ち、業務に集中できる環境を提供します。
特に、個別の作業が多い職場や、デスク上に多くの資料や機材が必要な場合に適しています。
固定席の最大のメリットは、社員が自身の作業環境をカスタマイズできる点であり、快適な作業空間を整えることで業務効率を向上させる効果があります。
ABW
ABW(Activity Based Working)は、社員がその時の業務内容に応じて自由に座席や作業エリアを選べる座席運用のスタイルです。
固定席を設けず、集中作業向けのエリア、会議やコラボレーションに適したスペース、リラックスできるラウンジなど、多様な作業環境をオフィス内に作り出すことができます。
この運用は、社員が最適な環境で業務を進められるため、効率性と創造性の向上が期待できます。
また、フレキシブルな働き方を促進し、オフィススペースを有効活用できる点が大きなメリットです。
フリーアドレス
フリーアドレスは、社員に固定席を設けず、空いている座席を自由に利用できる座席運用のスタイルです。
この運用では、社員が日によって異なる席を選ぶことができるため、柔軟な働き方が可能です。
特に、リモートワークや外出が多い職場では、座席の利用効率を高める効果があります。
また、座席を自由に選べることで、部署やチームを超えた交流が活性化し、組織内のコミュニケーションが向上するメリットもあります。
グループアドレス
グループアドレスは、社員全員に固定席を設けるのではなく、部署やプロジェクトチームごとに専用のエリアを割り当てる座席運用のスタイルです。
この方法では、各グループがエリア内の座席を自由に利用できるため、フリーアドレスの柔軟性と固定席の安定感を両立させることが可能です。
同じチームのメンバーが近くで働くため、コミュニケーションが取りやすく、業務の進行がスムーズになります。
また、チーム専用のエリアを持つことで、必要な資料や機器を効率的に管理できる点もメリットです。
オフィスレイアウトのポイント
オフィスレイアウトを考えるうえで重要なポイントは、以下の5つです。
- 動線を意識した配置を考える
- 部門ごとのエリア分けを工夫する
- 柔軟に変化できるレイアウト設計
- コミュニケーションを促進するスペースを設ける
- 設備や収納の配置バランスを調整する
それぞれのポイントについて詳しく紹介しますので、レイアウトに悩んでいる方は参考にしてみてください。
動線を意識した配置を考える
オフィスレイアウトを設計する際には、動線を意識した配置を考えることが重要です。
動線とは、社員や来客がオフィス内を移動する際の経路を指し、これを最適化することで業務効率や快適性が大きく向上します。
例えば、会議室やコピー機、共有スペースなど頻繁に利用される場所をアクセスしやすい位置に配置することで、無駄な移動を減らすことが可能です。
また、主要な動線が他の作業エリアを横切らないよう工夫することで、集中を妨げることなく業務を進められる環境を整えられます。
動線を意識した配置は、快適で効率的なオフィスづくりの基本であり、社員の満足度を高める重要な要素となります。
部門ごとのエリア分けを工夫する
オフィスレイアウトを設計する際、部門ごとのエリア分けを工夫することは、業務の効率化やコミュニケーションの円滑化に大きく寄与します。
同じ部門の社員が近くに配置されることで、情報共有やチーム内での連携がスムーズになり、迅速な対応が可能になります。
また、業務の性質に応じて配置を工夫することで、働きやすさを向上させることもできます。
例えば、静かな環境を求める部門には集中しやすいエリアを、頻繁に打ち合わせが必要な部門には会議スペースに近いエリアを割り当てると効果的です。
部門ごとのエリア分けを工夫することで、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えられます。
柔軟に変化できるレイアウト設計
オフィスレイアウトを考える際、柔軟に変化できる設計を取り入れることは、将来の成長や働き方の変化に対応するために重要です。
社員数の増減や部署の再編、新しい業務の導入など、企業を取り巻く状況は常に変化します。
そのため、可動式のパーティションやモジュール型のデスクを採用することで、レイアウトを簡単に変更できるようにするのが効果的です。
また、共有スペースやフリーアドレスエリアを設けることで、多様な働き方にも対応可能になります。
柔軟性を持たせたレイアウト設計は、変化に強いオフィス環境を作り出せるでしょう。
コミュニケーションを促進するスペースを設ける
オフィスレイアウトを設計する際、コミュニケーションを促進するスペースを設けることは、社員同士の連携を深め、チームワークを強化する上で重要です。
例えば、カジュアルな打ち合わせや雑談ができるリフレッシュエリアを設置することで、自然な交流が生まれやすくなります。
さらに、個別の集中スペースと対比させて、オープンで柔軟なエリアを設けることで、業務の効率化にも寄与します。
コミュニケーションを促進するスペースを工夫することで、社員同士の信頼関係が深まり、職場全体の雰囲気が活性化します。
設備や収納の配置バランスを調整する
オフィスレイアウトを設計する際、設備や収納の配置バランスを適切に調整することは、効率的で快適な作業環境を実現するために欠かせません。
収納スペースは、書類や備品の種類に応じて適切な場所に設けることで、無駄な移動や探す手間を省きます。
さらに、オフィス全体のデザインやスペース効率を考慮し、収納家具の大きさや配置を調整することで、作業空間を最大限に活用できます。
設備や収納のバランスを整えることは、業務効率と快適性を両立させるための重要なポイントです。
オフィスレイアウトは業者に依頼できる?
オフィスレイアウトの設計や内装工事は、専門の業者に依頼することで、より効率的かつプロフェッショナルな仕上がりとなります。
その際、物件選びからレイアウト設計まで一貫してサポートしてくれる業者を選ぶことが重要です。
オフィスバンクでは、豊富な物件情報をもとに、最適なオフィス探しをお手伝いするだけでなく、ご契約後のオフィスレイアウトや内装工事についてもご相談いただけます。
オフィス移転やリニューアルをお考えの方は、物件選びからレイアウト設計まで幅広く対応できるオフィスバンクに、ぜひご相談ください。
まとめ:働き方に合わせたレイアウトでオフィスを快適に
当記事では、オフィスレイアウトの配置事例や設計の考え方について紹介しました。
オフィスレイアウトは、社員の満足度を左右するだけでなく、業務効率も左右する問題です。
当記事でご紹介した事例を参考に、自社に合ったスタイルを選択して、業務効率化を目指しましょう。