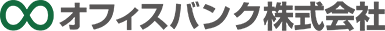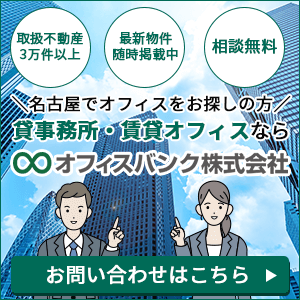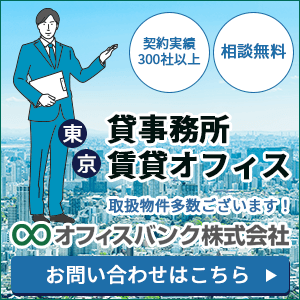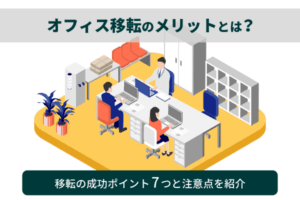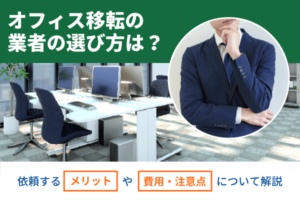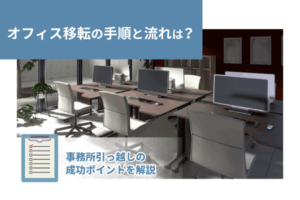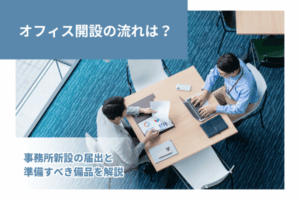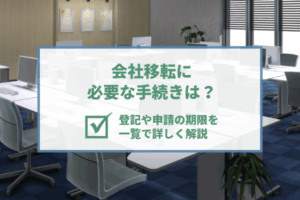「オフィスの原状回復とは?」
「原状回復工事の範囲や費用相場は?」
オフィスの原状回復とは、退去時にオフィスを入居時(契約開始時)の状態へ戻すことを指し、原則として、原状回復は借主の義務とされることが一般的です。
オフィス賃貸物件の原状回復において、通常損耗や経年劣化にあたる部分まで借主負担とする特約が組み込まれていることが多く、住宅賃貸とは扱いが異なります。
原状回復の範囲は、賃貸借契約に定められた特約によって大きく変わるため、契約書を詳細に確認することが極めて重要です。
オフィスの移転・退去を控える企業にとって、どこまでが原状回復に当たるのかを正確に見極めることは、余計なコストを防ぐうえでも欠かせません。
本記事では、原状回復工事の具体的な範囲や費用相場、注意すべきポイントを実務ベースでわかりやすく解説します。
オフィスの原状回復とは退去時に入居前の状態に復旧すること

オフィスの原状回復とは、賃貸オフィスを退去する際に、入居前の状態へ復旧することを指します。
原則として、借主が原状回復を行う「義務」を負うケースが多く、契約書に記載された内容や特約によって、範囲や費用負担が定められています。
以下に、原状回復で対象となる主な項目を一覧で整理しました。
| 原状回復の対象項目 | 内容例 | 備考 |
|---|---|---|
| 内装の撤去 | パーテーション、造作棚、間仕切り | 借主が設置したものは基本的に撤去対象 |
| 設備の撤去 | 空調、照明、LAN配線など | 原則、原状回復で取り外しが必要 |
| 壁・床の補修 | クロス張替え、床材の交換 | 汚れ・破損がある場合は修復が必要 |
| 看板・サインの撤去 | 社名プレート、案内表示 | 屋外設置物も対象になることあり |
上記のように、オフィスの原状回復では内装や設備、造作物など多岐にわたる項目が対象となり、借主側の対応範囲が広くなる傾向があります。
移転前に工事内容・費用負担の確認を行い、退去時のトラブルや余計なコストを防ぎましょう。
賃貸オフィスは賃貸住宅と比較して原状回復義務の範囲が異なる
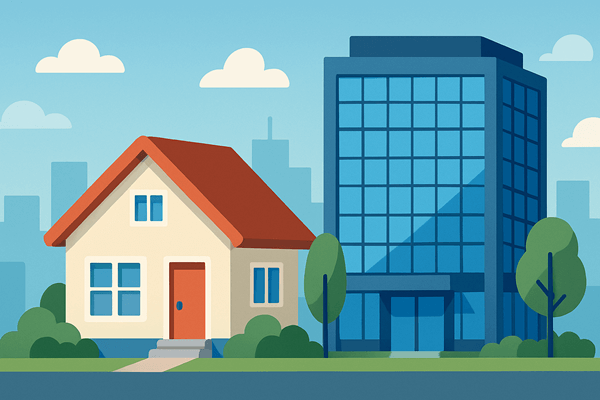
賃貸オフィスと賃貸住宅では、原状回復義務の範囲や考え方に大きな違いがあります。
一般消費者が借りる賃貸住宅(マンション・アパートなど)と比べて、事業者が借りるオフィス物件では、原状回復に関する特約の有効性が広く認められる傾向にあります。
賃貸住宅における原状回復義務は、民法621条や国交省のガイドラインによって「通常損耗・経年劣化は貸主負担が原則」とされており、借主にとって保護的な運用がなされます。
賃借人の原状回復義務
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
つまり、普通に生活している中でできた傷や汚れ(家具の跡や日焼けなど)は、退去時に借主が費用を負担する必要はありません。
一方、賃貸オフィスでは契約当事者間の合意(特約)が優先されるため、原則よりも広い範囲で借主が費用負担を求められるケースが多いのが実情です。
以下に、賃貸オフィスと賃貸住宅の原状回復に関する比較をまとめました。
| 比較項目 | 賃貸オフィス(事業用) | 賃貸住宅(居住用) |
|---|---|---|
| 契約の自由度 | 高い(特約で自由に設定可能) | 一般的に制限あり(民法・ガイドラインによる制約) |
| 原状回復義務の範囲 | 特約により拡張されることが多い | 通常損耗・経年劣化は原則貸主負担 |
| 通常損耗・経年劣化の扱い | 借主負担とする契約が一般的 | 借主負担は例外的扱い |
| 内装の撤去義務 | 借主が設置したものは原則すべて撤去 | 設置物が少ないため対象も限定的 |
オフィスの原状回復は費用負担が大きくなりがちで、契約トラブルも起きやすいため、事前に内容をよく確認しておくことが大切です。
オフィス原状回復工事の期間・費用相場と坪単価

オフィスの原状回復工事にかかる費用は、規模や工事範囲によって大きく異なります。
一般的には「1坪あたり2万円~7万円」が相場とされています。
また、工事期間は規模に応じて、数日から1カ月程度かかるのが一般的です。
費用には、内装の撤去、床材・クロスの張替え、電気・空調の復旧といった基本的な工事項目が含まれます。
スケルトン返却が条件の物件では、天井・壁・床すべてを原状に戻す必要があるため、費用が高くなりやすい点に注意が必要です。
以下では、オフィスの規模別の費用と工事期間の目安をまとめました。
| オフィス規模 | 坪単価の目安(税込) | 工事期間の目安 |
|---|---|---|
| 小・中規模オフィス(~50坪程度) | 2万〜5万円/坪 | 1週間〜2週間 |
| 大規模オフィス(50坪以上) | 3万〜7万円/坪 | 2週間〜1カ月程度 |
実際の費用は、使用年数や汚れ具合、造作物の多さによって変動します。
また、原状回復工事はオーナーに業者を指定される場合もあるため、契約書や管理規定の確認が重要です。
適正な費用でスムーズに退去するためにも、早めに見積もりを取り、複数業者の比較やスケジュールの確保を行いましょう。
オフィスの原状回復の流れは?賃貸借契約書の確認から引き渡しまで

オフィスの原状回復は、単に工事をすればよいわけではなく、契約条件やスケジュールに従って段階的に進める必要があります。
また、原状回復は工事後に追加工事が必要になる可能性があるため、事前確認が必要です。
オフィスの原状回復は、賃貸借契約書の確認から引き渡しまでの流れを把握しておくことで、トラブルを回避しながら退去まで進められます。
以下の各ステップを押さえておきましょう。
- 賃貸借契約書で原状回復義務の範囲を確認する
- 貸主指定以外の業者へ依頼できるか確認する
- 施工業者へ原状回復工事の発注と着工を依頼する
- 原状回復工事の完了後は立会いで貸主に確認してもらう
賃貸借契約書で原状回復義務の範囲を確認する
原状回復の第一ステップは、賃貸借契約書に記載されている原状回復の範囲や条件を確認することです。
賃貸借契約書には、「スケルトン返却」や「造作物の撤去義務」など、個別の特約が含まれていることがあります。
特約を見落としてしまった場合は、想定外の費用負担が発生する恐れがあるため必ず確認が必要です。
賃貸借契約書に「経年劣化も借主負担とする」などの特約がある場合は、クロスや床の張り替えまで求められることもあります。
オフィスの原状回復を行う前は、賃貸借契約書を確認し、不明な点があれば貸主や管理会社に相談しましょう。
貸主指定以外の業者へ依頼できるか確認する
オフィスの原状回復を行う前は、貸主指定以外の業者へ依頼できるか確認しましょう。
契約によっては、貸主指定の業者以外は認められないケースもあるからです。
貸主側には、ビル管理上の仕様や施工品質への一定の基準があるため、信頼できる業者に限定したい場合があります。
賃貸借契約書に「貸主指定業者でなければ不可」と記載されている場合は、借主が独自に業者を選んでも工事が認められず、再施工を求められるリスクもあるため注意しましょう。
費用を抑えるために相見積もりを取りたい場合でも、まずは契約書の業者指定条項を確認し、必要に応じて貸主の許可を取る必要があります。
施工業者へ原状回復工事の発注と着工を依頼する
原状回復義務の内容が明確になったら、施工業者に工事の見積もりを依頼し、発注・着工を依頼しましょう。
見積もり取得後に契約条件を確認し、内容に問題なければ発注に進みます。
工事の発注をスムーズに進めるためには「施工工程・作業時間・立会い日程など」を事前に業者と共有しておくことが大切です。
特にビルの規則や作業可能時間帯(夜間不可など)にも注意が必要です。
30坪のオフィスであれば、内装撤去・クロス張替え・清掃まで含めて1〜2週間程度が一般的で、スケルトン返却の場合は3週間以上かかることもあります。
工期の遅延は、退去日オーバーや追加賃料の発生につながります。
工事期間は余裕を持たせることで、突発的なトラブルが起きた場合でも、退去日までに間に合わせることが可能です。
退去日までに間に合わせるためにも、早めに業者を確定し、工程表に沿って作業を進めてもらいましょう。
原状回復工事の完了後は立会いで貸主に確認してもらう
原状回復工事の完了後は、立会いで貸主に確認してもらいましょう。
立会いでは、工事範囲や仕上がり・破損や汚損がないかなどを一緒にチェックが必要です。
貸主との立会いをすることで、契約上の原状回復義務を果たした証明となります。
立会い時も、工事部分の写真や確認書類などを保管し、記録を残しておきましょう。
なお、立会いによって万が一問題があった場合は、追加工事が必要です。
追加工事を防ぐためには、あらかじめ工事部分を確認しておくと回避できます。
以下では、オフィスの原状回復チェックリストをまとめました。
オフィスの原状回復をトラブルなく進めるためにも、以下のチェックリストを参考にしてみてください。
- 賃貸借契約書の原状回復条項を確認
- ガイドラインや管理規定をチェック
- 原状回復範囲(経年劣化含むか)を把握
- 貸主指定の業者制限があるか確認
- 工事業者の選定・契約
- 工期の調整と社内の退去スケジュールを合わせる
- 工事完了後の貸主立会い日程を確保
- 引き渡し後の敷金清算ルールを確認
- 工事完了報告書・確認書を保存
オフィスの原状回復を行う際の注意点とポイント
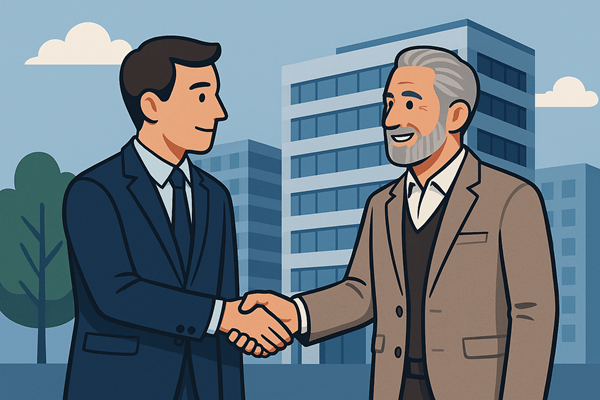
オフィスの原状回復を行う際の注意点とポイントは以下のとおりです。
- 複数の業者で見積もりを取る
- 原状回復工事の範囲を交渉しトラブルを防ぐ
- 原状回復のスケジュールを確認・設定する
- オフィスの移転時期は繁忙期を避ける
- 補助金や助成金の活用を検討する
- オフィスの原状回復に関する判例を参考にする
オフィス原状回復を進めるうえで押さえておきたい実務的な注意点と、失敗しないための具体的なポイントをわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
複数の業者で見積もりを取る
オフィスの原状回復工事では、必ず複数の業者から見積もりを取り、価格と工事内容を比較検討することが大切です。
複数の業者から見積もり取ることで、適正価格を把握し、過剰な工事や高額請求をする業者を避けることができます。
業者によっては「見積もりの内容、工事項目、追加費用」などの条件が異なる場合があります。
特にスケルトン返却など大規模な工事では、数十万円単位で差が出るでしょう。
一社目は「クロス全張替えが必要」と見積もる一方で、二社目は「一部のクロス補修で対応」と提案するケースも珍しくありません。
見積もりの違いを比較することで、自社にとって最適な工事内容を選ぶことができます。
一社だけで判断するのは、リスクが高いと言えるため、最低2~3社からから見積もりを取りましょう。
原状回復工事の範囲を交渉しトラブルを防ぐ
原状回復工事を進める際は、貸主と工事範囲について事前に交渉しトラブルを防ぎましょう。
契約書に「原状回復を要する」とだけ明記されていた場合は、具体的な範囲や内容がわからず、貸主との認識のずれが生じるからです。
契約書に工事範囲に関する記載がなかった場合は、借主と貸主との間で工事範囲の認識を合わせる必要があります。
認識のずれが起きるかもしれないと感じた場合は、通常損耗や経年劣化が含まれるか、造作物の撤去が必要かなどを確認しましょう。
また、工事範囲の確認は退去直前ではなく、事前に確認しておくことで原状回復工事もスムーズに進められます。
原状回復のスケジュールを確認・設定する
原状回復は、退去直前に慌ただしく進めるものではなく、数ヶ月前から計画的にスケジュールの確認をしましょう。
オフィス賃貸物件は、契約上の明け渡し期日に間に合わないと、高額な延滞金や違約金が発生する可能性もあるため、スケジュール管理は極めて重要です。
以下に、原状回復に向けたスケジュール設定の流れと、それぞれのフェーズで注意すべきポイントを表にまとめました。
| 時期の目安 | 主な作業内容 | 注意点・ポイント |
|---|---|---|
| 退去の2〜3ヶ月前 | 賃貸借契約書の確認 明け渡し日と原状回復義務の整理 | 特約・原状回復範囲を早めに把握しておく |
| 退去の1.5〜2ヶ月前 | 原状回復業者の選定・見積依頼 ビル管理会社への相談 | 工事の事前承認が必要な物件もある |
| 退去の1ヶ月前 | 業者と正式契約 工事日程の確定 | ビル使用ルール(作業時間・搬出入)の調整も必要 |
| 工事着工〜完了 | 原状回復工事の実施 中間立ち会い | 工事内容と契約条件が一致しているか進行中も確認 |
| 工事完了後〜退去日 | 最終立ち会い 鍵の返却 | 検収後の追加工事に備えて余裕を持って工程を組む |
契約終了日を鍵返却日とする物件も多く、追加工事の時間的猶予がないケースもあるため、余裕を持ったスケジューリングが不可欠です。
オフィスの移転時期は繁忙期を避ける
オフィスの移転時期は、繁忙期を避けることで工事費用やスケジュール調整を行いやすくなります。
年度末(3月)や9月などの繁忙期は、業者の予約が集中し、通常より費用が高くなったり、工期に遅れが出たりする可能性があるからです。
加えて、繁忙期は内装業者や不動産会社のリソースも限られるため、希望日に工事できない場合もあります。
オフィスの移転・退去は、繁忙期を避けることで、工事品質・スケジュール・費用面でも有利になります。
どうしても繁忙期と重なってしまう場合は、1週間~2週間ほど余裕を持っておくと安心です。
補助金や助成金の活用を検討する
オフィスの原状回復を行う際は、補助金や助成金の活用を検討しましょう。
国や自治体の制度のなかには、「省エネ改修」や「中小企業支援」などの名目で工事費の一部を補助する制度があるからです。
条件を満たすことができれば、関連する工事の一部に対して、補助金や助成金が活用できる場合があります。
加えて、経営革新枠を利用することで助成金の受け取りができます。
経営革新枠とはどんな枠ですか?
経営革新枠とは、事業承継やM&Aを契機として経営や事業を引き継いだ(または引き継ぐ予定である)中小企業者が、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行う際の費用の一部を補 助することで、中 小 企 業 者の生 産 性を向 上させることを目的とした枠です。
補助金や助成金は、管轄自治体の制度を確認し、対象となるか事前に調査しましょう。
活用できるか不安な場合は、専門業者や行政書士に相談するのも有効です。
オフィスの原状回復に関する判例を参考にする
移転する際は、オフィスの原状回復に関する判例を参考にしましょう。
判例を参考にすることで、借主としての権利や適正範囲を理解し、過剰請求を避ける判断材料になるからです。
実際に国土交通省の原状回復にかかる判例の動向では「経年劣化による損耗は借主負担ではない」と判断されたケースがあります。
過去の判例や情報は、貸主との交渉材料にも有効的です。
賃貸借契約書やガイドラインなど異なる工事を求められた場合は、法律専門家に相談し、根拠を持って主張することがトラブル回避につながります。
オフィスの原状回復も物件探しも「オフィスバンク」におまかせ

オフィス移転を検討しているなら、物件探しや原状回復工事・内装工事の手配もワンストップで行える「オフィスバンク」がおすすめです。
物件探しと工事の窓口を一本化することで、複数の業者とのやり取りやスケジュール調整といった煩雑さから解放され、スムーズなオフィス移転が実現できます。
オフィスバンクは、名古屋・東京エリアのオフィス物件を扱っている、30年以上の実績を持つオフィス賃貸専門不動産会社です。
これまで数多くの企業の移転・出店をサポートしてきた経験とノウハウで、立地・広さ・予算・契約条件など、事業に最適な物件をご提案します。
オフィスの原状回復に関するよくある質問

オフィスの原状回復に関するよくある質問を紹介します。
オフィスの原状回復では、基本的なルールや注意点が不明確なまま進めてしまうと、トラブルや追加費用の原因にもなりかねません。
以下では、特に質問が多い3点について、専門的な視点でわかりやすく解説します。
- オフィスに原状回復ガイドラインは適用されますか?
- オフィスの原状回復は通常損耗でも必要ですか?
- 原状回復工事の勘定科目は修繕費になりますか?
オフィスに原状回復ガイドラインは適用されますか?
オフィスに原状回復ガイドラインは、原則として適用されません。
オフィスや事務所の原状回復は、契約書に記載された内容が優先されるからです。
事業用契約では「スケルトン返却」や「造作物の完全撤去」など、住宅よりも厳しい内容が特約として記載されている場合があります。
経年劣化によるクロスの色あせの場合でも、契約書に「全面復旧」の記載があれば、借主側に負担義務があります。
オフィスの原状回復は、ガイドラインよりも契約書の内容が優先される認識を持っておきましょう。
オフィスの原状回復は通常損耗でも必要ですか?
オフィスの原状回復は、通常損耗の場合でも原則として借主負担になる場合が多いです。
一般的な居住用物件では通常損耗は貸主負担となりますが、オフィス契約(事業用物件)では、契約書に「通常損耗も含めて原状回復を行うこと」と明記されていることがあり、契約時の特約条項が優先されます。
オフィスの原状回復では「通常損耗=免責」とは限らず、壁紙の色あせや床材のすり減りといった部分も借主負担となる可能性があります。
原状回復工事の勘定科目は修繕費になりますか?
原状回復工事の会計処理においては、原則として「修繕費」として処理することが可能です。
ただ、内容や金額に応じて「資本的支出(資産計上)」となる場合もあります。
国税庁の取り扱いでは、原状回復工事が建物の価値を高める目的ではなく、通常の状態に戻すためであれば「修繕費」に該当します。
入居中に設置した「間仕切りの撤去、床の張り替え、塗装の補修」などは、退去に伴う必要経費として処理されるのが一般的です。
一方で、資産の性能を高めたり、使用可能年数を延ばしたりする改修工事を含む場合は、「資本的支出」と判断されることがあります。
原状回復工事の勘定科目は、税理士や会計士に確認した上で判断するのが確実です。
オフィス原状回復のポイントを押さえてスムーズに移転しよう
オフィス移転時の原状回復は、契約内容や工事範囲によって費用や対応が大きく変わるため、早い段階での準備が不可欠です。
原状回復のポイントを事前に把握することで、予想外のトラブルや追加費用を避け、スムーズなオフィス移転を実現できます。
また、「オフィスの原状回復工事」に関する情報収集や見積もりの比較も、移転コストの最適化につながる重要なステップです。
企業イメージや業務効率にも関わるオフィス移転だからこそ、原状回復の基礎知識をおさえた上で、計画的に進めましょう。